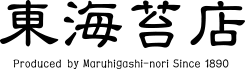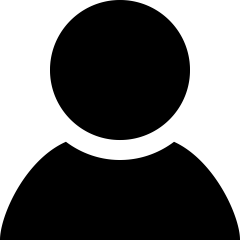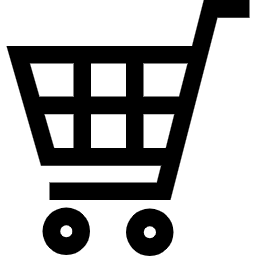おむすび?おにぎり?

こんにちは、きかねこです!
さて、突然ですがアナタは
「おむすび」派?「おにぎり」派?
それとも別の呼び方をする?
昔話「おむすびころりん」では「おむすび」だし、お店では「おにぎり」が圧倒的に多いような気がします。
どっちが正しいのか気になった方も多いのでは?

きかねこは生まれも育ちも広島なので、
「おむすび」の方がしっくりくるのですが、
表記の時に困るんですよね・・・。
日常的に食べるお弁当から、運動会などの行事まで日々の定番であるこちらの呼び名から。
■呼び方の違い■

・おにぎり
関東で主に使われます。全国的にはこちらの呼び名が多いかも!
・おむすび
関東から東海道、中部から中国地方で使われています。
・にぎり・にぎりめし
九州、沖縄ではこちらを使います。

中部地方の名古屋は「天むす」があるので、納得!
■名の由来■
・「おにぎり」→鬼切りの語呂合わせという説も。
昔話の中では、投げて鬼をやっつけることもあるそうです。
・「おむすび」→「むすぶ」心(魂)をそこに込め、心臓の形になっているそうです。(柳田國男説)
などの様々な諸説があります。
呼び名も違えば、形もそれぞれ異なったりします。
■形の違い■
・三角
関東地方発祥
・俵
関西に多い。一説には味付け海苔が巻きやすいから、この形になったそうです。

・丸
九州、中部地方に多い。
・円盤
東北地方に多い。味噌を塗ったり、焼きおにぎりにしやすい。
また、各地方の文化、ライフスタイルに合わせて形状もそれぞれ異なるようです。

巻くものも海苔に限らず、富山県ではとろろ昆布を巻いたり、
広島県は広島菜を巻いたりなど、
色々あります。
また歴史も古く、弥生時代の遺跡から握り飯の化石も見つかっています。
平安時代の書物にも「屯食(とんじき)」という名で出てきます。
移動の時にも、持ち運びが便利ということで、太古の昔から日本人に愛される、まさにソウルフード!
平安時代などは、まだ一般に海苔が出回っておりませんので、
米を握っただけでしたが、
江戸時代に海苔の養殖が始まり、一般市民も海苔を手に出来るようになってから
今のような海苔を巻いた形になりました。
地域などによって様々ですが、
実のところ、呼び名のルールなど正確にはわかっていないようです。
この記事を読んでおにぎりに興味を持ったアナタ!
こちらの本もおススメです♪
「にっぽんのおにぎり」著:白央 篤司
なんと全国のおにぎりを紹介しています。
この本を読んだらお腹が空いて旅をしたくなること間違いなし!?

以上、個人的に密かに疑問だったことでした☆
完全な解決とはいきませんでしが、なんとなくスッキリ!?
この辺りの研究は今もされているそうなので、いつかはっきりわかるといいな~♪